<岡城と岡藩> 
文治元年(1185)平安末期南北朝時代に大野川の中流に勢力をもっていた緒方三郎惟栄(これよし)が後白河法皇の命で義経を連れて来る途中で難破し、上野国沼田莊(現在の群馬県沼田市)に流罪になる。その時に義経を迎えるために惟栄が岡城を築いたといわれている。形が牛の寝ている姿に似ていることから臥牛城とも呼ばれる。
建久7年(1196)鎌倉幕府から豊前、豊後の守護職として大友能直(よしなお)が任命され、速見郡浜脇浦から上陸し緒方一族を滅ぼした。後醍醐天皇の命で大友氏の分家になる大野莊志賀村南方に住む直入郡代官の志賀貞朝が、騎牟礼(きむれ)城<現竹田市飛田川にあった。地域俗称地名古城(ふるしろ)と呼ばれている地区>から岡城に入城し本丸を築くなどの大改修を行い以後志賀氏代々の居城となる。
天正14年(1586)に秀吉の九州征伐の命で薩摩の島津義久の軍3万余の攻撃を受けたがわずか18歳の城主志賀親次(ちかよし)は千名ほどの兵で3度の攻撃を退け難攻不落の城として名を轟かせた。
文禄2年(1593)秀吉の朝鮮出兵で出陣していた大友氏の当主大友義統(よしむね)が敵の大軍来襲で逃走したため秀吉の怒りをかい、改易され岡城城主であった志賀氏も追放された。
文禄3年(1594)2月播磨国(兵庫県)三木城から中川秀成が4千人ほどの人を連れ城主となった。秀成は城の大改修にかかかた。
慶長元年(1596)完成した本丸には三層三階の三重櫓天守と藩主居住の本丸御殿を築いた。二の丸に数寄屋、月見櫓、御風呂櫓などの遊興的曲輪、三の丸には使者の間、小姓詰所及び三十畳の広間などがあり藩主の執務場所だったと思われる。武器庫を整備、さらに大手口、近戸口、下原口のような登城口搦め手などを整備。
寛文4年(1664)西の丸が完成。三代藩主久清が建てたが隠居後の住まいに使用された。
元禄2年(1689)年以降西の丸は藩主の居住所や藩政執務などに使われるようになった。江戸時代後期はここが藩政の中心場所になった。
天明4年(1784)廟所に家老屋敷、先祖代々の位牌所などが完成。
城郭は東西に延びる台地に山城で建築形態は山城的殿舎形態の曲輪(くるわ)の廟所と平山城的殿舎形態の曲輪の本丸、二の丸、三の丸、平城的殿舎形態の西の丸からなっている。城郭の中心になる本丸、二の丸、三の丸は東西の中仕切によって区切られている。(下図参考)
中川氏は12代続いて岡城を継いだ。
明治2年(1869)に12代藩主久昭は版籍奉還を申請し、岡藩知事に任命される。
明治4年(1871)版籍奉還以降は岡藩の各地で一揆が起こったり他藩の脱藩者などが潜入するなど非常に不安定な状況が続いたため、一揆を鎮圧した後、久昭は息子久成に家督を譲り隠居した。久成は明治政府に恭順を示すため、地震などで天守や櫓の老朽化が激しいのもあって岡城を取り壊す。
同年7月に廃藩置県により岡藩は岡県となり岡藩知事だった久成は免官となり帰京を命じらる。またさらに政府は11月にはさまざまな規模の県を統合し大分県とした。
※廟所は藩主の先祖を祀るなどの施設

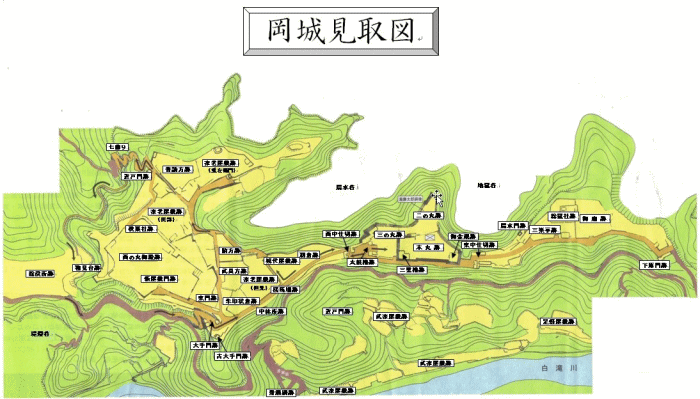
岡城見取図拡大図PDF
※愛染堂から見た岡城(この画像はflashプレーヤーが必要です)
<岡城の出入>
城への出入りは各門ごとに厳しく行われた。門は通常明六ツ(午前8時)に開き、暮六ツ(午後6時)に閉じた。閉門以後の出入りは禁止だが、特別な事情の時だけ藩の重職を担う者に限り通行が許されていた。
城内の主な門には大手門、近戸門、下原門、太鼓櫓門などがありそれぞれの門には役職としての門番である侍番が置かれた。太鼓櫓門は本丸、二の丸、三の丸への関門として重要な門であり、出入りは厳しく管理されていた。この太鼓櫓は時を知らせる役割があり、火事の際には鐘と一緒に鳴らすという重要な役割もあった。
城の来客は身分などにより城内の通行や案内が違い、所用で登城した者には城代家老の許可が出るまで門を入ることが出来なかった。町民は急用な使者であっても門の入口までしか行けず門番に用件を伝達した。
藩に関係する豪商は総役所に献上品を届け、城内には案内人により案内され賄方で待機し、別な案内人により用事のある殿舎に行く。殿舎の入口で案内人が替わり中へ通される。
(観光案内巻物より)
建久7年(1196)鎌倉幕府から豊前、豊後の守護職として大友能直(よしなお)が任命され、速見郡浜脇浦から上陸し緒方一族を滅ぼした。後醍醐天皇の命で大友氏の分家になる大野莊志賀村南方に住む直入郡代官の志賀貞朝が、騎牟礼(きむれ)城<現竹田市飛田川にあった。地域俗称地名古城(ふるしろ)と呼ばれている地区>から岡城に入城し本丸を築くなどの大改修を行い以後志賀氏代々の居城となる。
天正14年(1586)に秀吉の九州征伐の命で薩摩の島津義久の軍3万余の攻撃を受けたがわずか18歳の城主志賀親次(ちかよし)は千名ほどの兵で3度の攻撃を退け難攻不落の城として名を轟かせた。
文禄2年(1593)秀吉の朝鮮出兵で出陣していた大友氏の当主大友義統(よしむね)が敵の大軍来襲で逃走したため秀吉の怒りをかい、改易され岡城城主であった志賀氏も追放された。
文禄3年(1594)2月播磨国(兵庫県)三木城から中川秀成が4千人ほどの人を連れ城主となった。秀成は城の大改修にかかかた。
慶長元年(1596)完成した本丸には三層三階の三重櫓天守と藩主居住の本丸御殿を築いた。二の丸に数寄屋、月見櫓、御風呂櫓などの遊興的曲輪、三の丸には使者の間、小姓詰所及び三十畳の広間などがあり藩主の執務場所だったと思われる。武器庫を整備、さらに大手口、近戸口、下原口のような登城口搦め手などを整備。
寛文4年(1664)西の丸が完成。三代藩主久清が建てたが隠居後の住まいに使用された。
元禄2年(1689)年以降西の丸は藩主の居住所や藩政執務などに使われるようになった。江戸時代後期はここが藩政の中心場所になった。
天明4年(1784)廟所に家老屋敷、先祖代々の位牌所などが完成。
城郭は東西に延びる台地に山城で建築形態は山城的殿舎形態の曲輪(くるわ)の廟所と平山城的殿舎形態の曲輪の本丸、二の丸、三の丸、平城的殿舎形態の西の丸からなっている。城郭の中心になる本丸、二の丸、三の丸は東西の中仕切によって区切られている。(下図参考)
中川氏は12代続いて岡城を継いだ。
明治2年(1869)に12代藩主久昭は版籍奉還を申請し、岡藩知事に任命される。
明治4年(1871)版籍奉還以降は岡藩の各地で一揆が起こったり他藩の脱藩者などが潜入するなど非常に不安定な状況が続いたため、一揆を鎮圧した後、久昭は息子久成に家督を譲り隠居した。久成は明治政府に恭順を示すため、地震などで天守や櫓の老朽化が激しいのもあって岡城を取り壊す。
同年7月に廃藩置県により岡藩は岡県となり岡藩知事だった久成は免官となり帰京を命じらる。またさらに政府は11月にはさまざまな規模の県を統合し大分県とした。
※廟所は藩主の先祖を祀るなどの施設

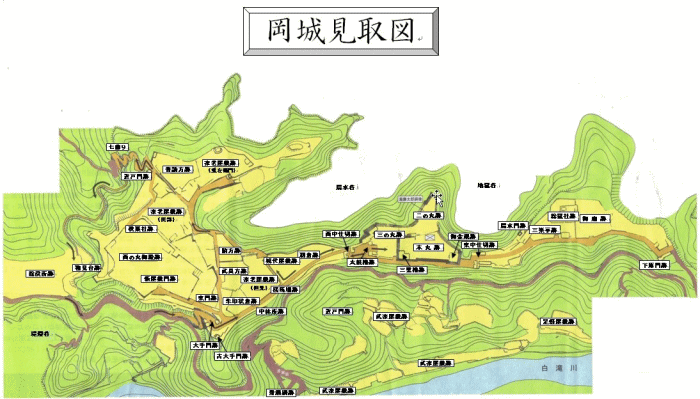
岡城見取図拡大図PDF
※愛染堂から見た岡城(この画像はflashプレーヤーが必要です)
<岡城の出入>
城への出入りは各門ごとに厳しく行われた。門は通常明六ツ(午前8時)に開き、暮六ツ(午後6時)に閉じた。閉門以後の出入りは禁止だが、特別な事情の時だけ藩の重職を担う者に限り通行が許されていた。
城内の主な門には大手門、近戸門、下原門、太鼓櫓門などがありそれぞれの門には役職としての門番である侍番が置かれた。太鼓櫓門は本丸、二の丸、三の丸への関門として重要な門であり、出入りは厳しく管理されていた。この太鼓櫓は時を知らせる役割があり、火事の際には鐘と一緒に鳴らすという重要な役割もあった。
城の来客は身分などにより城内の通行や案内が違い、所用で登城した者には城代家老の許可が出るまで門を入ることが出来なかった。町民は急用な使者であっても門の入口までしか行けず門番に用件を伝達した。
藩に関係する豪商は総役所に献上品を届け、城内には案内人により案内され賄方で待機し、別な案内人により用事のある殿舎に行く。殿舎の入口で案内人が替わり中へ通される。
(観光案内巻物より)
